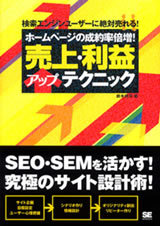東京・北区赤羽駅前の行政書士村上事務所です。貸金業登録、会社設立、遺産、相続、遺言、離婚相談、消費者トラブル、内容証明、契約書作成と全国からの相談をおこなっています。
 |
●携帯サイトはこちら● ★会員サイトはこちら★ |
| 無料相談はこちら 電話:050−3045−7910(9〜20時) 携帯:090−3521−1188(8〜21時) お急ぎの方は携帯電話におかけください |
 |
3つの相続方法 行政書士相談
相続財産には、現金、不動産、預貯金などのプラスの財産だけでなく、住宅ローンや借金などの
マイナスの財産も含まれることになります。そのためマイナスの財産がプラスの財産を超えてしまう場合には、相続人が借金などの債務を返済していかなければなりません。
相続人が被相続人の借金で苦しまないように、民法では3つの相続の方法が用意されています。
1.単純承認
最も一般的な相続方法で、被相続人の財産の一切を継承する方法です。この場合は特別な手続をする
必要はなく、相続開始後3ヶ月以内に他の手続をとらなければ、
自動的に単純承認をしたものとみなされます。しかし、
被相続人にマイナスの財産がある場合には、その借金を遺産の中から優先的に債権者に
支払わなければいけません。
2.相続放棄
被相続人の財産を放棄し一切の財産を相続しない方法です。
被相続人の遺産よりも借金の方が多い場合には、この方法を取るのがいいでしょう。
相続人が被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、
それが認められれば相続人ではなくなりますので、被相続人の負債を負わされることはありません。
※第1順位の相続人が相続を放棄した場合は、第2順位、第3順位へと相続人が代わりますから、
場合によっては相続人になる全ての者が相続放棄をする必要があります。
3.限定承認
相続財産が預金、不動産、株等のプラス財産から借金等のマイナス財産がある場合、プラス財産から
マイナスの財産を差し引いて得た財産の範囲内で借金を返済するという方法です。
仮に財産を清算した結果、借金だけしか残らない、、、、不足分を支払う必要はありません。
一方、借金を返済して財産の方が多ければ、差し引いた財産については取得することができます。
限定承認の手続は、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、
家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出して行います。
※限定承認はメリットがあるように思われますが、
非常に手間と時間がかかる上、法定相続人が複数いる場合には
必ず全員で手続をしなければならないことにも注意が必要です。
3ヶ月以内に限定承認も放棄もしないと民法は単純承認したとみなします。
(5) 遺言状の内容
せっかく残した故人の財産をめぐって相続人間で争いがおきないよう遺言状を書き残しておきましょう。
遺言状がなければ、民法に定めた相続割合に応じて法定相続人が相続することになります。
遺言は死人に口なし、そこで民法の定める厳格な書き方、形式が
不可欠なのです。相続が親族間の争族、骨肉の争いにならないように遺言状を残しておきましょう。
誰が遺言状を書けるのか?
年齢があります 満15才以上であればOKです。
遺言能力、つまり判断能力があれがよいのです。
成年被後見人でもできます。二人以上の医師の立会いが必要です。
文字が書けなくても、言葉が喋れなくても遺言ができます。
どんな内容が遺言できるのか?
■ 認知→いわゆる隠し子にも財産を与えるとか。
■ 遺贈→相続人以外のものに財産を与えるとか、他人、息子の妻とか。
■ 遺贈についての減殺方法→息子の妻には土地をあげ、他の相続人とは金で解決とか。
■寄付行為→蔵書は図書館に寄付とか。
■ 相続分の排除、排除の取り消し→次男にはあげないとか。
■ 遺産分割方法の指定→土地は長男に、預金は次男にとか。
■ 共同相続人の担保責任の指定→家の修繕代金は次男が持つようにとか
■ 相続分の指定、指定の委託→○○さんの指示通りに分けろとか。
■ 祭祀をおこなう者→祭りごとは長男が主宰せよとか。
■ 遺言状はいつでも、何度でも変更できます。
■ 遺言状は公正証書にしておくほうが確実です。
■ メール相談 電話相談 会って相談
(6) 遺言状の作成方法について
その1 自筆遺言証書→遺言者が遺言内容を書き、日付、氏名、自書押印すること
裁判所の検認が必要となります。勝手に開封しないでください。
その2 秘密遺言証書→遺言者が遺言内容を秘密にできる。
交渉役場の手数料がかかる
無効になることはない
裁判所の検印は不要
公正証書遺言
作成方法 二人以上の証人が必要
紛失、変造の恐れがない
遺言内容を秘密にできる
簡単に一人でできる ただし紛失、変造の疑いがあれば無効
その3 公正証書遺言→二人以上の証人を立ち合わせ、遺言者が公証人に遺言内容を伝え、
公証人が筆記して読み聞かせます。間違いなければ各人が自署押印します。
公正証書遺言は、それ自体に執行力があるので家庭裁判所の持ち込むことなしに執行できます。
それに公証役場に遺言書正本を預けることになり、盗難、紛失、変造の危険がなくなります。
遺言に万全を期しておきたい方は公正証書遺言がおすすめです。
遺言執行者を決めておくこともできます。
公正証書遺言作成のご依頼は下記まで
ご相談=>
その4 特別方式→緊急時の遺言です。証人3人以上の立会いを得て、その1人に内容を伝え、
証人は内容を筆記して確認しあいます。
(7) 遺産分割の方法について
遺言状があれば遺言通りに分配の話し合いが始まりますが、遺言書が無いときときは、
相続人全員が参加する遺産分割協議によって各人に分配することになります。
遺産分割協議は「遺産に属する物または権利の種類(預金、農地etc)、各相続人の年齢、職業、
心身の状態及び生活の状況、性別、結婚ノ有無、その他一切の事情を考慮して
これをする」と民法で定められています(906条)。
遺産分割協議に相続人全員が参加していなかった場合は、
その遺産分割協議は無効となります。また、相続人が遺言で包括遺贈しているような場合は、
包括受遺者も相続人と同様の地位とされますので、は包括受遺者協議に参加する必要があります。
遺産の分割方法は次の3種類があります。
■現物分割
遺産そのものを物で分ける方法です。
現物分割は、各相続人の相続相当分通りに分けることは困難なので、
相続人間の取得格差が大きい場合には、その分を他の相続人に金銭で支払うなどして
清算することが多いです。
■代償分割
相続分以上の財産を取得する場合において、その代償として他の相続人に金銭を支払う方法です。
■換価分割
遺産を売却して金銭に換え、金額を分ける方法です。
現物を分割してしまうと価値が低下する場合などはこの方法がとられます。
この方法は、遺産を処分してしまうので、処分に要する費用や譲渡所得税などがかることがあるので
注意が必要です。
遺産分割協議はあくまで、相続人間での話し合いです。たとえ遺言書がある場合でも、
受遺者は放棄することができ、法定相続分とは違う分け方にすることもできます。つまり、
相続人全員で協議し、全員が賛成すれば遺言や法定相続分に関係なく、
財産をどのように分けても自由なのです。
法定相続人の見分け方
遺産を引き継ぐ人は民法という法律で決められています。
残された親族が誰であるかによって相続できる人と
相続できる割合が異なってきます。
(8) あなたは相続人ですか?
民法の定めにより相続人となれる人を「法定相続人」といいます。
法定相続人に常になれる人は配偶者です。他には、(1) 子(第一順位)→(2) 父母(第2順位)→
(3) 兄弟姉妹(第3順位)と優先順位があります。
つまり、(1) 〜(3) は同時に相続人とはなれないということです。
詳しくはお問い合わせ下さい。
法定相続人を表でチェックしましょう!
法定相続分
配偶者、子ともに1/2ずつ相続します
配偶者と父母がいる場合
(子はいない)→配偶者が2/3、父母が1/3を相続します
配偶者と兄弟姉妹がいる場合
(子も父母もいない)→配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を相続します
配偶者のみいる場合
(子も父母も兄弟姉妹もいない)→配偶者が全てを相続します
配偶者がいない場合で、
子・父母・兄弟姉妹いる場合→子供が全てを相続します
遺言執行人の就任業務について
遺言書の内容をとどこうりなく実現するため、遺言者は遺言執行人を決めて書いておくことができます。
通常は遺言状で選任されますが、相続人が家庭裁判所に申し立てできます。
遺言執行人は、財産目録の作成、遺産の管理・処分などをまとめることができます。
相続人から遺言執行者を選ぶこともできますが、利害関係のない第三者を選ぶことをおすすめします。
Q,相続人調査ってどうやるの?
A、相続人を確定するための手続きである相続人調査は、亡くなった方が生まれた時から亡くなるまでの
戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を取得することから始まります。これに、亡くなった方の子などの戸籍も集め、法律上相続人を探していくのです。
Q,戸籍謄本は郵送で取り寄せられますか?
A,戸籍・除籍謄本は、本籍地や以前の本籍地の市区町村の戸籍の担当の窓口に直接請求するか郵送で請求することで取得できます。
札幌の人が、東京にある戸籍を、札幌の役所で取ることはできません。
あくまでも本籍地の役所でないと取れないのです。
行政書士相談(板橋区、北区、足立区、川口市、埼玉、池袋) 内容証明
![]()
![]()
| 会社設立 |
| 遺産相続 |
| 示談書 |
| 著作権 |
| 内容証明郵便 |
| 国際 |
| 許認可 |
| 行政書士について |
| 相談 |
| 各種データ |
| ブログ |
| リンク |
| 特定商取引法による表示 |